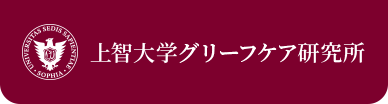ご挨拶
上智大学グリーフケア研究所長 竹内 修一

日々の生活の中で、私たちは、さまざまな出来事を体験します。その中には、楽しいこともあれば悲しいこともあります。悲しいことの原因としては、自然災害、人災・事故、そして病気などが考えられます。これらは、自分の意志とは関係なく生じます。できれば、そのようなことは避けたい——それは、人間の自然的な感情からすれば、極めてあたりまえのことでしょう。
「グリーフケア」における「グリーフ」(grief)は、「悲嘆」あるいは「深い悲しみ」と訳されます。多くの場合それは、自分にとって大切な人やことが、何らかの理由で失われたときに体験する喪失感でしょうか。この喪失感は、個人的なレベルのものもあれば、世界的・地球的なレベルのものもあります。例えば、紛争や戦争などによって経験する平和の喪失などは、その最たるものでしょう。
一方、「グリーフケア」における「ケア」(care)は、人間と人間との全人格的な交わりであり、すべての人が本来、人間としてもっている他者に対する思いやりであり心遣いです。それゆえケアは、ただ単に医師や看護師などの専門的活動に限定されるものではありません。そのことを、シモーヌ・ローチは、次のように語ります——「ケアリングは、人間の存在様式です。」
「心は心に語る」——それは、心を込めて自分の思いを相手に伝えようとするなら、きっとそれは相手の心に届くということです。いわば、心と心の共鳴です。グリーフケアは、この延長線上にあります。
先ほども確認しましたように、私たちは、できれば苦しみや悲嘆は避けたいと思います。しかしそれらは、ただ単に否定的なものではなく、その背後には、私たちが学ぶべき何らかの大切なことがあるのではないか、とも考えられます。同時にまた、それらは、ただ自分一人で担わなければならないものではありません。むしろ、お互いに助け合い担い合ってゆくべきものなのではないか、とも考えられます。
私たちは、どのようにグリーフケアを学ぶことができるでしょうか。まず私たち自身が、自らの悲嘆の体験を振り返り、それが自分の人生においてどのように位置づけられるのか、そのことを思い巡らします。それによって、この体験は経験となり、真に生きた知恵となります。そのうえで、専門的な知識があれば、いっそうこの知恵は確かなものとなり、他者の悲嘆に共感し寄り添い、何らかの手伝いや助けも可能となるのではないでしょうか。